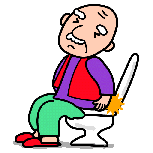 |
|
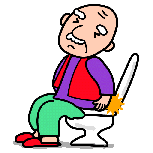 |
|
| 1) 痔核 痔核は一般に「いぼ痔」と呼ばれ、痔疾患の約半数を占めます。 痔核はこれまで直腸肛門部の静脈の網の目(静脈叢)がふくらんだ病気(静脈瘤)と考えられていましたが、最近では 痔核の部分は単に静脈叢だけではなく、細かい動脈や筋肉・繊維組織などが含まれていて、肛門を閉鎖するのに役立つクッションだということがわかってきました。 そして排便や日常生活からくる肛門への負担により、クッションを支えている支持組織がのびたりちぎれたりして、このクッション自体が大きくなることが痔核の原因と考えられるようになってきました。 痔核は内痔核と外痔核にわけられます。 内痔核は、肛門上皮と直腸粘膜の境目(歯状線)よりも奥(直腸粘膜側)にある痔核をさし、外痔核はこの歯状線よりも手前(肛門上皮側)にある痔核をさします。一般に痔核の初期の段階では内痔核として始まり、進行して大きくなってくると血栓性外痔核を伴った一つのふくらみ(内外痔核)となる場合が多いです。時には血栓が原因となり外痔核のみが膨張する外痔核となることもあります。内痔核が肛門外に脱出するようになると「脱肛」とも言います。 痔核の原因としては、便秘や下痢などの便通異常による肛門部への負担がまず第一と考えられます。そのほかにも運転やデスクワークなどの長時間座りっぱなしの姿勢でいることによる肛門のうっ血、激しい力仕事や運動、妊娠や出産、アルコールや香辛料などが肛門部に負担をかけ痔核の原因となりえます。 痔核の主な症状は出血と脱出です。通常は痛みを伴わない鮮やかな色の出血であることが多く、紙に付く程度のものからほとばしり出るようなものまで様々です。出血の頻度もたまに出血するだけであったのが次第に増え、ひどくなると排便のたびに出血するようになります。 脱出は始めのうちは排便のときに出て排便の後には自然に元に戻っていますが、次第に手で押さないと戻らない状態となり、やがて排便時以外にも脱出するようになります。 診断は肛門鏡という器具を使って痔核の部位・大きさや脱出の程度を確認します。出血の原因として直腸に癌やポリープが存在しているときもあるので、注腸X線検査や大腸内視鏡検査を行います。 |