
アスピリン探検隊 (3) |
| ◆解熱作用 |
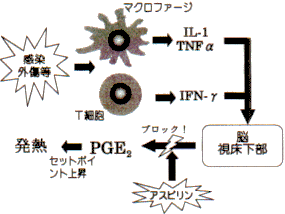 ヒトの脳の祝床下部にある体温調節中枢は熱の産生と放散を調整し、体温を一定に保っています。
ヒトの脳の祝床下部にある体温調節中枢は熱の産生と放散を調整し、体温を一定に保っています。体温調節中枢では体温セットポイントと比較し、脳の温度が低いと熱産生及び皮膚血管の収縮を促し、脳の温度 が高い場合は発汗と皮膚血管拡張を促します。 発熱とは、感染や炎症などにより生じたサイトカインであるインターロイキン1(IL―1)、腫瘍壊死因子(TNF−α)、インター フェロンγ(INF−γ)など内因性発熱物質が体温調節中枢においてPGE2産生を促進させ、体温のセットポイントを上昇させている状態と考えられています。 高熱がでる前に寒気やふるえがおこるのは、セットポイントが上昇し熱産生が促進されるためです。 アスピリンはPG合成抑制により、セットポイントを正常に戻し解熱作用を示します。 |
| ◆鎮痛作用 |
|
組織に炎症が起こるとプラジキニン、ヒスタミンなどの発痛物質が作られ、痛覚受容器を刺激して痛みがおきます。 更にブラジキニンは組織細胞膜のPLA2を活性化し、その過程でPGを産生します。 PGは知覚神経終末で痛みの閾値を下げることにより、ブラジキニンの発痛作用を増強させます。 アスピリンはCOX阻害により、PGの合成を抑制し鎮痛作用を示します。 |
| ◆抗炎症作用 |
|
発赤、浮腫、疼痛といった炎症反応にはヒスタミン、ブラジキニン、LT類、PG類などのさまざまなメディエーターが関与してい
ます。 また、これらは、PLA2を活性化し、PGE2、PGI2などの産生を促進します。 PGE2、PGI2はそれ自体炎症惹起作用は弱いですが、ヒスタミン、ブラジキニンの血管透過性亢進作用を増強し浮腫を引き起こすなど、炎症反応に関与しています。 アスピリンはCOX抑制によりPG合成を抑制し、抗炎症作用を示します。 |